塗装の現場において、道具は職人の「相棒」とも言える存在です。どれだけ経験があっても、使う道具が不適切なら仕上がりに差が出てしまう。それほど道具選びと扱い方は重要です。特に塗装工として現場に入るなら、どんな道具を使っているか、その名前と役割を知っておくことが、最初の理解の一歩になります。
まず、もっとも基本となるのが「刷毛(はけ)」と「ローラー」です。壁や天井など広い面を塗るためのローラーと、角や細かい部分に対応する刷毛は、それぞれ役割が異なります。加えて、塗装面以外を保護するための「養生テープ」や「マスカー」なども欠かせません。
これらは現場で毎日のように使う道具であり、使い方を覚えることで少しずつ塗装の工程全体が見えてきます。今回は、そうした基本装備の名前と役割を、未経験の方でも理解しやすい形でひとつずつ解説していきます。
刷毛にも種類がある?プロが使い分ける理由
「刷毛」とひとことで言っても、その形や用途はさまざまです。現場では、「筋違(すじかい)」「目地刷毛(めじばけ)」「寸胴(ずんどう)」など、名前を聞いただけでは想像しにくい刷毛がたくさん登場します。それぞれの違いを知ることで、塗装作業の細やかさや奥深さが見えてきます。
筋違刷毛は、先が斜めにカットされた形状をしており、角や隅など、細かい箇所の塗装に最適です。目地刷毛はその名の通り、サッシ周りや隙間、凹凸のある部分の塗装に向いています。寸胴刷毛は毛の密度が高く、広めの面をしっかりと塗るのに使われます。これらはただ見た目が違うのではなく、「塗料の含み方」「仕上がりの質感」「疲労度」にも影響を与えます。
また、毛の素材にも違いがあり、人工繊維か天然毛か、あるいはその混合かによっても、滑らかさや塗りムラの出方が変わります。職人たちは、現場の状況や使う塗料の種類によって、最適な刷毛を選んで作業します。
未経験者のうちは、刷毛の種類や名前を覚えるだけでも大変かもしれませんが、現場で触れていくうちに、それぞれの特徴と使い分けの感覚が少しずつ身についていきます。「なぜ先輩はその刷毛を使ったのか」を観察する姿勢が、上達への近道になります。
ローラーの違いは毛の長さだけじゃない
ローラーは「広い面を一気に塗る」ための道具ですが、その種類は意外なほど多く、適当に選ぶと仕上がりにムラが出てしまいます。毛の長さや素材の違いはもちろん、芯の硬さや持ち手の長さなど、作業性に直結する細かい要素がいくつもあります。
毛の長さには「短毛」「中毛」「長毛」があり、それぞれ用途が異なります。短毛ローラーは仕上がりが滑らかで、室内の壁や天井に向いています。中毛はバランスが良く、外壁や多用途に使われることが多いです。長毛ローラーは、でこぼこした壁やモルタルなど、凹凸の多い面に塗料をしっかり乗せたいときに適しています。
また、塗料によっては、毛の素材との相性も重要になります。水性塗料にはナイロン素材が、油性塗料にはウール素材のローラーが適していると言われます。こうした細かな違いを意識せずに使うと、塗料が飛び散ったり、思ったような色にならなかったりすることがあります。
持ち手(ハンドル)の長さも用途に応じて使い分けます。天井や高い壁を塗るときは延長できるハンドルを使うことで、安全性も確保できます。現場によってはローラーの洗い方まで決まっており、使い終わった道具をどう手入れするかも職人の大事な仕事です。
ローラー選びは単なる「道具選定」ではなく、現場を読み、仕上がりを想像する力が問われる判断でもあります。
養生こそ命。テープ・マスカー・シートの選び方
塗装の仕上がりを左右するのは、実は「塗る作業」そのものではなく、塗る前の準備——なかでも「養生(ようじょう)」の丁寧さです。養生とは、塗らない部分をテープやシートで保護する工程のこと。例えばサッシやガラス、床面、照明器具など、塗料が飛んでほしくないところをあらかじめ覆っておく作業です。
よく使われるのが「養生テープ」。これは粘着力が強すぎず、剥がしても跡が残りにくいのが特徴です。加えて、「マスカー」と呼ばれる道具もあります。これはビニールシートとテープが一体化したもので、広い面を素早く覆うのに便利です。たとえば窓や玄関など、風で汚れが飛びやすい場所ではマスカーが重宝されます。
床面などには「ノンスリップシート」や「ブルーシート」を使うこともあります。滑りにくく、繰り返し使えるため、安全と効率を両立できるのが利点です。これらを現場に応じて使い分けることで、作業中の事故防止にもつながります。
養生は、ただの下準備ではなく、塗装工としての「丁寧さ」を問われる工程です。慣れないうちはテープをまっすぐ貼るだけでも苦戦するかもしれませんが、これがきちんとできると、塗装後の仕上がりがぐっと引き締まります。養生の精度で、その職人がどこまで現場を大切にしているかが伝わる。そう言っても過言ではありません。
プロが道具にこだわる理由とは?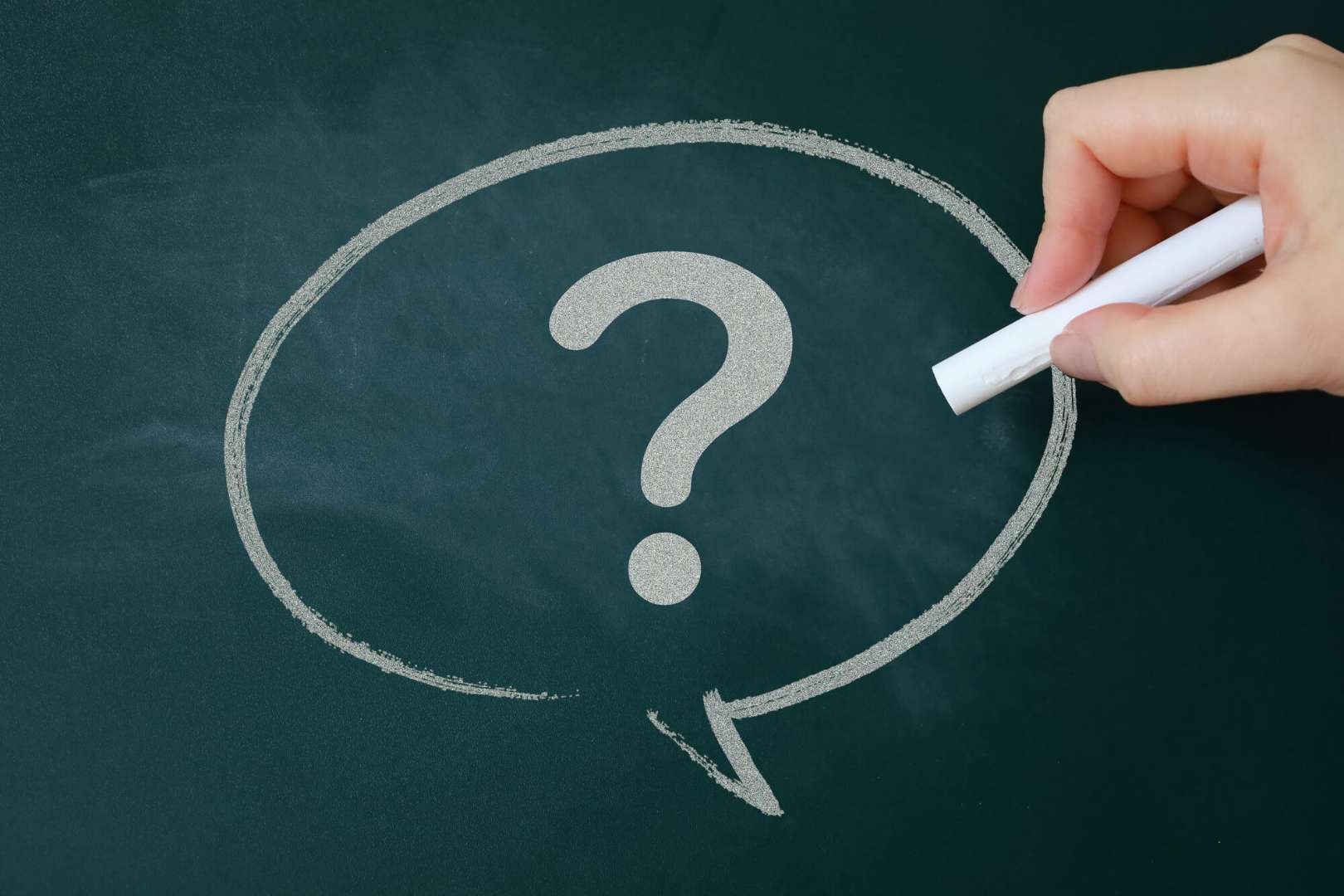
一流の職人ほど道具にこだわります。それは単に「高いものを使えばいい」という話ではなく、「自分の技術を正しく表現できる道具」を選び抜いているからです。たとえば同じ刷毛でも、持ち手の太さや毛の弾力によって手に馴染む感覚が変わります。手に合わない道具を無理に使えば、疲労や塗りムラにもつながり、結果として仕上がりが落ちてしまうのです。
また、道具をきれいに保つこともプロの証です。使ったローラーや刷毛をしっかり洗って乾燥させる。そうした日々の手入れを怠らない職人ほど、長く安定した仕事を続けていける傾向があります。これは「道具を大事にする=仕事に責任を持つ」姿勢そのものとも言えます。
株式会社グラフトのように、品質にこだわる塗装会社では、現場で使う道具の選定や整備が徹底されています。現場の状況、塗料の種類、塗装する素材の特性に合わせて、何を使うか、どの順番で作業するかが細かく判断されるのです。
こうした現場に身を置くことで、「なぜこの道具なのか」を自分なりに考える力が自然と養われていきます。未経験でも、最初から一流の道具を使う必要はありません。でも、先輩たちがどんな基準で道具を選んでいるかを観察し、自分の中に蓄積していくことは、確実に成長への土台になります。
→ https://www.ltd-graft.jp/recruit
道具を知れば、現場がもっと見えてくる
塗装の現場における道具は、単なる「作業の手段」ではありません。それぞれの名前や役割を理解することで、現場の動きが立体的に見えてきます。たとえば、ローラーの毛丈や刷毛の形が違うのは、現場にそれだけ多様なニーズがあるということ。養生に使うテープやシートも、場所ごとに最適な選択肢が求められます。
道具を知るということは、職人の仕事を理解する第一歩でもあります。名前を覚えることが目的ではなく、その道具が「なぜ必要か」「どう使うと良いか」を考える習慣を身につけることで、作業そのものへの理解が深まっていきます。
もし現場に興味が出てきたら、まずは少し道具に注目してみてください。それだけで、塗装という仕事の奥行きや工夫の跡が見えてくるはずです。


